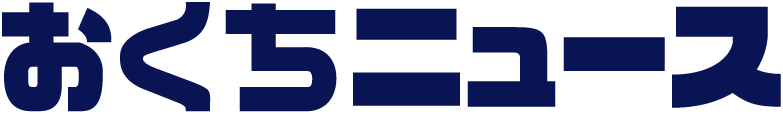目次

くしゃみが臭い原因
くしゃみが臭い原因は、食事や生活習慣の影響だけでなく、口内環境や細菌の繁殖、膿栓(臭い玉)なども関係しています。まずは、くしゃみが臭くなる主な原因について詳しく解説します。
外的な要因
くしゃみが臭い原因のひとつは、食べ物や生活習慣の影響です。にんにくやネギなどニオイ の強い食材を含む料理を食べた後は、口の中にニオイが残りやすく、くしゃみをしたときに強いニオイを感じやすいです。
また、飲酒後も、アルコールが分解される過程で発生するニオイの成分が、口臭の原因になります。さらに、喫煙は唾液の分泌を抑え、口内の乾燥を招き、ニオイの原因菌を増やす要因です。
口の中の乾燥
口の中が乾燥すると、口臭の原因になる嫌気性細菌(けんきせいさいきん)が繁殖しやすくなります。嫌気性細菌は、酸素が少ない環境を好むため、唾液が減少して口の中が乾くと活発に増殖するのが特徴です。口の中が乾燥した状態が続くと、くしゃみをした際に強いニオイを感じやすいでしょう。
また、食べカスや歯垢が残ったままだと嫌気性細菌のエサとなり、よりニオイが強くなります。
膿栓(臭い玉)
膿栓(のうせん)は、通称「臭い玉」とも呼ばれる白や黄白色の小さな塊で、サイズは5~6mm程度です。喉の奥にある扁桃腺のくぼみに溜まり、細菌や食べカスが固まって形成されます。
膿栓は多くの場合、くしゃみや咳をしたときに自然に排出されます。しかし、放出されなかったときは強い悪臭を放つことがあります。膿栓が原因の場合、くしゃみをした瞬間に強いニオイを感じることが多いです。
臭い玉については、下記の記事で紹介しています。
「臭い玉とは?取り方や予防方法を解説」
マスクの長時間着用
マスクを長時間着用すると、口の中が湿った状態になります。口内の湿度が高まると細菌が繁殖しやすい環境が生まれるため、口臭が悪化します。
細菌の増殖によって発生したニオイは、くしゃみをした際に一気に放出されるため、強く感じることがあるでしょう。

くしゃみが臭いときの対処法
くしゃみのニオイが気になる場合、唾液の分泌を促したり、口内環境を整えたりすることで、ニオイの原因を減らすことが可能です。ここでは、効果的な対処法について解説します。
よく噛んで食べる
唾液には口の中を浄化し、ニオイの原因菌を抑える働きがあります。唾液の分泌を促すために、食べるときはよく噛んで、口周りの筋肉を刺激しましょう。
意識的に噛む回数を増やすだけでなく、食後にガムを噛むのも効果的です。特にキシリトール入りのガムは唾液の分泌を促し、口臭予防にも役立ちます。唾液量を増やせば、くしゃみのニオイを軽減できるでしょう。
唾液腺マッサージをする
唾液腺マッサージは、口臭の原因となる細菌の繁殖を抑える効果的な方法です。口の中には、耳下腺(じかせん)、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)の3つの唾液腺があり、これらを適切に刺激すれば唾液の分泌量を増やせます。それぞれの唾液腺を刺激するマッサージ方法について解説します。
耳下腺(じかせん)のマッサージ
耳下腺は耳の前、上の奥歯あたりに位置する唾液腺です。優しく刺激すると、唾液の分泌を促せます。下記の手順で、マッサージを行いましょう。
1.指をあてる
指を数本、耳の前、上の奥歯付近にあてます。
2. 円を描くようにマッサージする
後ろから前に向かって円を描くように、指全体で優しく10回ほどマッサージしましょう。
強く押しすぎると痛みを感じることがあるため、リラックスして優しく行うのがポイントです。
顎下腺(がっかせん)のマッサージ
顎下腺は、あごの骨の内側にある柔らかい部分に位置している唾液腺です。ここも適切に刺激すると、唾液の分泌を促進できます。下記の手順でマッサージを行いましょう。
1.親指をあてる
親指をあごの骨の内側の柔らかい部分にあてます。
2. 耳の下からあごの下まで押す
耳の下からあごの下まで、5か所ほどに分けて順番に押しましょう。各ポイントをゆっくりと5回程度押して刺激します。
力を入れすぎず、痛みを感じない程度に行いましょう。
舌下腺(ぜっかせん)のマッサージ
舌下腺は、あごの先端の内側にある唾液腺で、刺激すると唾液の分泌をさらに促すことができます。下記の手順でマッサージを行いましょう。
1. 親指をそろえてあてる
両手の親指をそろえて、あごの尖った部分の内側にあてます。
2. あごの真下から押し上げる
親指であごの真下から上方向にゆっくり押し上げるように加圧しましょう。
3. 10回ほど繰り返す
力を入れすぎず、10回ほど優しく押し上げます。
舌回しエクササイズをする
舌回しエクササイズは、舌を動かして口周りの筋肉を刺激し、唾液の分泌を促進する効果があります。舌の先端で上下の歯茎をなぞるように動かす簡単なエクササイズなので、いつでも実践しやすいです。
右回りに10回、左回りに10回を1セットとして、1日3回程度続けると唾液量が増え、口臭の原因となる細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。
うがいをする
うがいをすると口腔内が潤い、粘膜に付着した細菌やウイルスを効果的に洗い流せます。「あー」と声を出しながらうがいをすれば、喉が振動して膿栓(臭い玉)が取れやすくなります。
定期的にうがいをすることで、口の中が清潔に保たれ、くしゃみのときのニオイの原因を減らせます。喉の乾燥を防ぐ効果も期待できるため、日常的に取り入れたい習慣です。
ストレスを溜めない
唾液腺は、自律神経によってコントロールされており、リラックスしているときにより多くの唾液が分泌されます。ストレスが溜まると唾液の分泌が減り、口臭の原因になるのです。
時間を選ばず手軽にできるリラックス方法として、深呼吸があげられます。仕事の合間や家事の合間など、日常生活に取り入れてみてください。
また、普段シャワーで済ませている場合は、週に1回ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることで、ストレス解消になるでしょう。

ニオイが改善されない場合は病気の可能性もある?
これまで紹介した原因に気を付けていても、くしゃみのニオイが改善されない場合、病気が関係している可能性があります。ここでは、口臭につながる病気について詳しく解説します。
虫歯や歯周病
虫歯や歯周病は、口臭の大きな原因です。虫歯になると、歯にできた穴に虫歯菌が溜まり、ニオイの発生源になります。
一方、歯周病の場合は、歯茎の炎症によって出血や膿が発生し、そのニオイがくしゃみをしたときに外に放出されます。
虫歯菌や膿が原因で口臭が強くなるため、早めの治療や定期的なケアが重要です。
副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔は、鼻の中にある8つの小さな空間の総称です。風邪のウイルスやアレルギーが原因で鼻が腫れたり、鼻水で副鼻腔と鼻をつなぐ通路が塞がれたりすると、副鼻腔に膿や鼻水が溜まり、副鼻腔炎を引き起こします。
この状態は「蓄膿症」とも呼ばれ、膿が喉に流れ込むと、口臭やくしゃみの際にニオイの原因になります。
扁桃炎
扁桃炎は、喉の奥にある扁桃腺に炎症が起こる病気です。膿栓(臭い玉)が扁桃腺に大量に溜まると、細菌が繁殖して炎症を引き起こすことがあります。
膿栓が溜まった状態が続くと、くしゃみをした際に強いニオイを感じます。扁桃炎は口臭の原因にもなるため、膿栓を溜めないように日頃からのケアが重要です。
胃腸のトラブル
胃腸の調子が崩れると、食べ物の消化吸収に時間がかかり、体内で発酵して悪臭ガスが発生します。このガスは血流に溶け込み、全身を巡った後、肺から呼気として排出されることで口臭の原因になります。
胃腸の不調が続くと、くしゃみをした際にも強いニオイを感じることがあるため、食生活の見直しや胃腸のケアが大切です。

まとめ
くしゃみが臭い原因は、食生活や口内環境、膿栓、病気など多岐にわたります。日頃のケアや生活習慣の改善で口臭の軽減は十分に可能です。それでも改善しない場合は、虫歯や副鼻腔炎などの病気が原因の可能性もあります。原因に応じた適切な対策を行い、くしゃみのときの不快なニオイを軽減しましょう。
【関連記事】
口臭を改善したい!主な原因と今すぐ始められる改善策や予防策を紹介