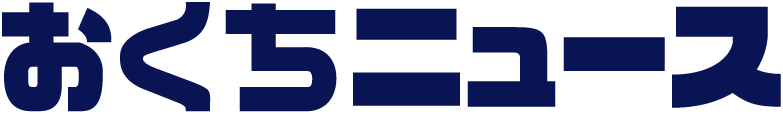目次

歯に着色汚れがつきやすい人の特徴
歯に着色汚れが付着してしまう理由は、日々の行動にあります。毎食後に必ず歯磨きを行っているという人も、ちょっとした行動が着色汚れの原因となる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、以下のような行動を取っている人は、歯に着色汚れがつきやすくなります。
タバコを吸っている
タバコを日常的に吸っていると、ヤニによって歯が全体的に黄ばんだり、一部に茶色い汚れがこびりついたりします。
ヤニによる汚れは、一度付着すると落としにくい特徴があります。歯科医院でも完全に落とすのが困難なため、喫煙習慣のある人は注意しましょう。
着色しやすい食べ物をよく食べている
普段口にする食べ物や飲み物の中にも、着色しやすいものがあります。代表的なものは、以下の通りです。
・コーヒー
・お茶
・カレー
・ケチャップ
・ワイン
歯の着色汚れは、ステインとも呼ばれます。
色の濃い食べ物には、ステインのもととなるポリフェノールやタンニンが含まれていることが多くあります。ポリフェノールなどの成分が歯のエナメル質を覆っているペリクルに付着することで、着色汚れが生じてしまうのです。
歯並びが悪い
喫煙の習慣がなく、色素の濃い食べ物や飲み物を取る機会も少ない人でも、歯並びが悪い場合は注意が必要です。着色汚れの原因のひとつは、歯に付着した色素をきちんと落とせないことにあります。
歯並びが悪いと、隅々まで十分に汚れを落とすことが難しい傾向にあります。磨き残しを放置しておくとさらに落としにくい歯石となり、歯の表面にこびりついてしまいます。歯石自体にも汚れが付着しやすいため、着色汚れはさらに悪化するでしょう。
口呼吸をしている
口呼吸をする癖がある人も、歯が汚れやすい傾向にあります。理由は、口呼吸によって口内が渇き、唾液が少なくなってしまうためです。
唾液は口内を潤すと同時に、汚れを洗い流してくれる役割も持っています。口呼吸を繰り返すと汚れを洗い流してくれる唾液が十分に出ないため、汚れは落ちにくく歯の表面に残るリスクが高くなります。
歯磨きの仕方に問題がある
歯磨きの仕方を誤っていると、歯に着色汚れが蓄積する原因となることがあります。以下の点について心当たりがないか、確認してみましょう。
・研磨剤が含まれていない歯磨き粉を使用している
・歯磨きの頻度が少ない
・歯磨きをしていない
・歯磨きの時間が不十分である
研磨剤は歯の表面に付着した汚れを落とす役割を持つ成分です。使用量が多すぎたり歯磨きをしすぎたりすると歯を傷つけるリスクもありますが、まったく使用しないと汚れが落ちにくくなります。
また、歯磨きの頻度が少なかったり(1日に1回、数日に1回など)、歯磨きの時間が極端に短かったりすると歯垢が歯に残りやすく、時間が経つと歯石に変わってしまいます。
歯石は歯磨きだけでは取り除けなくなり、さらに着色汚れが目立ちやすくなります。

歯の着色汚れを取る方法
歯の着色汚れを取る方法として、以下の4つがあげられます。
研磨剤入りの歯磨き粉を使う
研磨剤入りの歯磨き粉は、市販でも手軽に購入でき、ヤニやステインもある程度落とす効果があります。まずは、毎日の歯磨きに研磨剤入りの歯磨き粉を取り入れてみましょう。
ただし、「強く磨きすぎない」「長時間磨きすぎない」「歯磨き粉を多くつけすぎない」ことを意識することが大切です。研磨剤を多く使いすぎると歯の表面に傷がつき、かえって着色汚れが生じやすくなります。
歯科医院でクリーニングする
歯科医院は虫歯ができたときにのみ通う、という人は少なくないでしょう。しかし、歯科医院は虫歯治療のほかに口内トラブルの予防や対処も行っています。専門的な用具で行うクリーニングも歯医者で受けられる施術のひとつです。
自分自身では磨き残してしまう部分の汚れや、歯石となってこびりついた汚れも除去してもらえます。あわせて虫歯チェックも行ってもらえるため、歯の健康のためにも定期的な検診がおすすめです。
歯専用の消しゴムを使う
歯の表面に付着した部分的な汚れを除去したいときや、前歯を重点的にケアしたいときに便利なのが、歯専用の消しゴムです。消しゴムのように歯の表面を擦ることで、多少の汚れを除去できます。
ペン型や消しゴム型など、販売されている形状はさまざまです。機能に大きな差はないため、自分に合った形状のものを選びましょう。
ただし、使用頻度と使い方には注意が必要です。
商品によっては研磨剤が含まれているものがあり、日常的に使用したり、力を入れて擦りすぎたりすると、歯の表面を覆っているエナメル質が削られてしまうおそれがあります。
また、エナメル質が薄くなることで、歯の内部の象牙質が透けて見えるようになり、かえって歯が黄ばんで見えてしまうこともあります。エナメル質の損傷が進むと、冷たい飲み物などの刺激に敏感になる「知覚過敏」の原因になりかねません。
このようなリスクを避けるためにも、歯の消しゴムは週に1~2回程度の使用にとどめ、力を入れすぎず優しく使用することが大切です。
日々の歯磨きを基本とし、気になる部分をケアしたいときの補助的なアイテムとして、上手に取り入れていきましょう。
ホワイトニングをする
着色汚れを落とすだけでなく、歯を今よりも白く見せたい場合、ホワイトニングがおすすめです。
ホワイトニングとは、専用の薬剤や溶液を使って歯の色そのものを明るくする方法です。
ホワイトニングには4種類の方法があり、それぞれ特徴や持続期間が異なります。ライフスタイルや希望に合わせて、適切な方法を選ぶことが大切です。
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングは、自宅で自分のペースで行えるホワイトニングです。歯科医院で自分専用のマウスピースを作ってもらい、処方された薬剤とともに使用します。
毎日一定時間装着することで、少しずつ歯が白くなっていきます。即効性はありませんが、その分効果が長持ちしやすいのがメリットです。
オフィスホワイトニング
歯科医院で本格的に施術してもらうホワイトニングです。専用の高濃度薬剤と特殊な光を使って短時間で効果を得られるのが特長で、1回の施術でも白さを実感できるケースが多いとされています。
そのため、イベント前や早く歯を白くしたい方におすすめの方法といえるでしょう。
セルフホワイトニング
セルフホワイトニングは、専用サロンで自らケアする方法です。専用の溶液や機器を使って歯を本来の白さへ近づけることができ、自然な仕上がりが魅力です。
ホワイトニングの中でも比較的安価でケアできる一方で、歯が白くなるまでに時間がかかります。
デュアルホワイトニング
自宅でのケアと歯科医院での施術を組み合わせる「デュアルホワイトニング」は、効果の高さと持続性の両方を兼ね備えた方法です。
オフィスホワイトニングで歯を白くした後に、ホームホワイトニングでその効果を長く保つことができます。そのため、デュアルホワイトニングは、本格的にホワイトニングしたい人におすすめです。
ホワイトニングの種類については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
「ホワイトニング4種を比較!白さを長持ちさせるポイントは?」

歯の着色汚れの予防
着色汚れのケアも重要ですが、毎日の予防も欠かせません。予防によって歯に付着する汚れを軽減できれば、ケアの手間や費用も抑えられます。
最後に、手軽にできる歯の着色汚れの予防方法を紹介します。
歯科医院に定期的に通う
歯石除去やホワイトニングを受けた後も、毎日の食事などによって再び汚れが蓄積します。
一度ケアをしたとしても、きれいな状態を維持し続けられるわけではないため、こまめに歯科医院でクリーニングを受けましょう。目安として、最低でも半年に1回は歯科医院に相談することをおすすめします。
着色の原因になる飲食物の過剰摂取を控える
コーヒーやワイン、ケチャップなど、着色汚れが生じやすい食べ物・飲み物に注意しましょう。特に一部の飲み物は日常的に口にする人も多いため、好んで飲む人は意識して回数を減らすことが重要です。
食後の歯磨きを欠かさない
食後はこまめに歯磨きを行いましょう。飲食後に歯磨きの習慣を身に付けると、虫歯予防にもつながります。
また、飲み物のように歯と歯の間に浸透するものもあります。うがいも意識して行うと、より着色予防が期待できるでしょう。
タバコを控える
タバコのヤニは着色汚れにつながりやすい上、通常の歯磨きでは十分に落とせません。研磨剤入りの歯磨き粉で多少は軽減できますが、大きな効果にはつながらないため、タバコ自体を控えることをおすすめします。
タバコは健康被害のリスクもあります。歯の着色汚れが気になる人は、思い切って禁煙に挑戦してはいかがでしょうか。
口呼吸にならないように意識する
口呼吸は、唾液による自浄作用が十分に働かず、着色汚れが落ちにくくなるだけでなく、口内の雑菌を増やす原因にもなります。歯周病や虫歯になるリスクが高まるため注意が必要です。そのため、日常的に鼻呼吸を意識し、口呼吸にならないよう気を付けることが大切です。
口呼吸の原因を確認し、鼻炎や慢性的な鼻づまりなどがある場合は、耳鼻科での治療が必要になるケースもあります。また、意識的に鼻呼吸をするよう心がけたり、舌を上顎にしっかりとつけておく習慣をつけたりすることで、口呼吸を予防できます。
就寝中に無意識に口が開いてしまう方には、専用のテープを口に貼って眠るのがおすすめです。テープを貼ることで、無理なく口の開きを抑えられるでしょう。
とはいえ、自力での対処が難しい場合は、歯科医院でトレーニングを受ける方法もあります。出っ歯や受け口といった歯並びが原因の場合は、歯列矯正を検討することで、根本的な解決につながることもあります。

まとめ
歯の着色汚れが気になる人は、まず生活習慣に問題がないか振り返ってみましょう。普段口にするものや、無意識でしている行動が原因となっていることがあります。
自分に合った予防や対処を行い、悪化させないよう心がけましょう。
▼監修者プロフィール
中谷 一空(なかたに かずあき)
医療法人社団一志会 木更津きらら歯科 理事長
福岡歯科大学医科歯科総合病院の歯周病科および口腔インプラント科にて臨床経験を積み、現在は「木更津きらら歯科」の理事長として、予防から審美・インプラントまで幅広い歯科医療に携わる。
専門性の高い治療技術と豊富な知識を活かしながら、患者一人ひとりの悩みに丁寧に寄り添い、安心・安全で納得感のある医療提供を心がけている。
警察歯科医・海上保安歯科医としての公的活動をはじめ、美容・アンチエイジング・スポーツ歯科など多分野にも対応。長年にわたる臨床と地域医療への貢献が認められ、東久邇宮国際文化褒賞を受賞するなど、幅広い実績を持つ。
所属学会・資格:
日本歯周病学会 認定医/日本口腔インプラント学会 専門医/国際口腔インプラント学会(ICOI:FELLOW)認定医/国際コンテンポラリー歯科学会(iACD) 理事/日本歯科審美学会 会員/日本スポーツ歯科学会 会員/アジアアンチエイジング美容協会 名誉顧問/臨床研修指導歯科医/木更津市 警察歯科医/海上保安歯科医
※一部の内容(歯の消しゴム、ホワイトニングマニュアルに関する記述)は、医師監修対象外です。